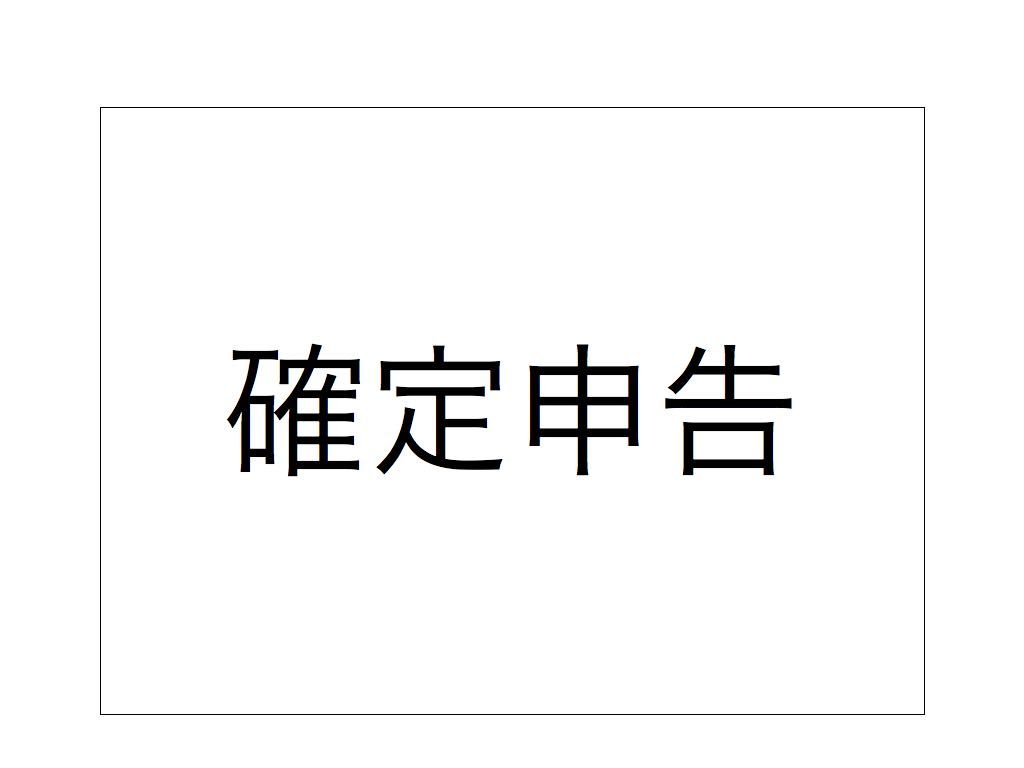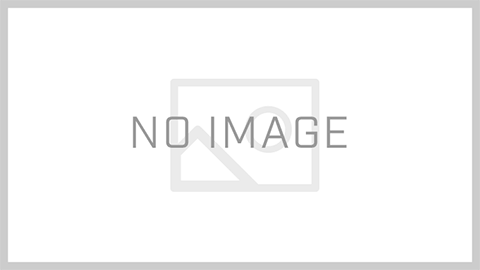熊本でのボランティアのある日、帰りの団体バスの中。
車内の通路を挟んで反対側に座っていたおばさん2人(失礼だけれどそう呼称する/おそらくひとりは自分の母親くらいの年齢)が偶然にも僕と同じ宿泊場所だと知って、少し話をした。
ひとりは神奈川県、もうひとりは北九州市からの参加で、宿泊場所で知り合ってからいっしょに行動しているようだった。
バスが到着後、いっしょに昼ご飯を食べようと誘われ、他のおじさんもひとり加わった。4人で「太平燕」というラーメンのようなもの(熊本の名物らしい)を食べ、瓶ビールをごちそうになった。
食事が終わって店を出ると、おばさん2人は買い物をしてから帰るとどこかへ行ってしまい、おじさんは今日から同じ宿泊場所へ泊まるらしかったので、いっしょに市電に乗って案内した。
・・・
滞在中、この3人とは顔を見れば話をするようになって、おばさん2人からはコーヒーやお菓子、ビールなんかと、しっかりしなさい的な言葉をもらった(よほど頼りなさそうに見えたのかもしれない)。
もらうばかりで悪かったので、何かお返しにとコンビニやスーパーを回った結果ファミマで無印良品のお菓子を買い、僕が帰る日の朝に手渡した。
また、そのほかにも少し話をした人は、その後も見かけたら挨拶をしたり話しかけたりした。めずらしく自身にそうしようという意志があり、容易な雰囲気がその場の人たちにあったので。
そしてそのような(関係性が固定される)ことをかなりの場面で回避してきた自分にとっては、稀で新鮮な体験で、面倒だとはあまり思わなかった。(だからそういうことをしたければ、ボランティアに参加するのも一つの方法だと思います)
・・・
圧倒的な個人の集まりで、その場限りの出会いだから、別に誰とも話さなくてもいい。だけど完全にそうなるとけっこうつらい。
あの場で関係性が生まれやすかったのは「共通意識(=ボランティア)」があることももちろんだけれど、「おじさん・おばさん的な存在」がたくさんいたことも大きい。哲学者の鷲田清一は下記のように語っている。
「まち」とひらがなで呼ばれるようなコミュニティには、おじさん・おばさん的な人が多かったと思う。
その人たちは子どもたちに関心はあるし、親身ではあるけれど、親ではないので責任はない。少し距離をおいて、でもどこかでいつも気にはかけてくれている。そんな人間関係が、実の叔父・叔母ではなく、近所のおじさん・おばさんとの間にあったと思うんです。
それは子どもにはうっとおしい。ちょっと出かけようとすると「どこ行くんや。えらいめかしてんな」とか(笑)。「うるさいな」って気分になるし、見られてない方がいいと思うけど、誰かが見てくれている、気にかけてくれていることで、安心感を得ていたりもする。
このおじさん・おばさん的な距離感は、さっきの「Unique I」と「One of them」の中間的なあり方なんです。
親は「Unique I」をくーっと押しつけてくる。都市は「One of them」という、何の関係もないサッパリとした関係性である。その矛盾の中間にいるのが、おじさん・おばさんかな。
(西村佳哲『自分の仕事を考える3日間』p234)
「Unique I」「One of them」については下記のとおり。
中川久夫という精神科医は、このことをこんな風に語っています。
唯一の私、掛け替えのない私が「Unique I」。代わりもきくし、特別な存在でもない多くの中の一人としての私のあり方は「One of them」。
彼は、「Unique I」であると同時に「One of them」というこの矛盾に安心して乗っかっていられるようになることが、人間として成熟するということなんだって言っています。
(同書p232)
僕が(岡山県の)地元を好きな理由のひとつに、こういった関係性がまだ残っていることもある(もちろんそれがイヤで出て行く人もいると思うし、徐々に関係性が無くなっている気もする)。
携帯で連絡しなくてもふらっと友達の家のチャイムを押すような感じだったり、ジョギング中に声をかけられたり。都会的なマッチョな場所はつらくて暮らせそうにない。いま住んでいるところ(岡山市内)は1mmもないんだけれど。
また、年齢が離れている人というのは、(僕の場合)自意識のようなものを感じないで済む。自分は自分/他人は他人と割り切れる。逆に年齢が近いと、どうしても相対化しにくかったりして、距離を置いてしまいやすい。
「人間として成熟する」というのは言葉として高尚でおこがましい気がするので、自分がやりやすい距離感や中間点を見つけていくようなことだと思う。